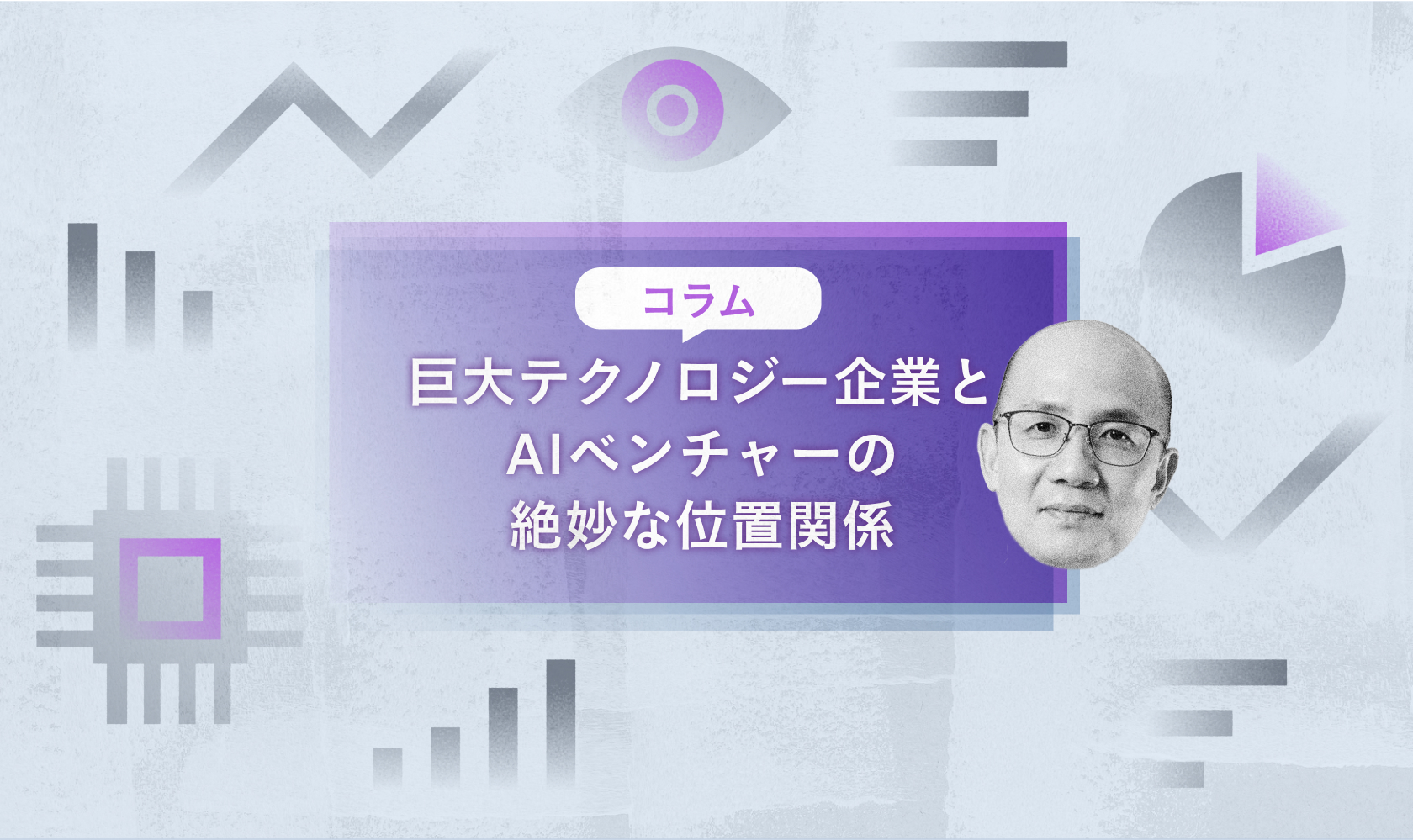ChatGPT(チャットGPT)をはじめとした生成AIが注目を集めている。日常生活の中でも生成AIを個人的に使用している人も多くなってきたとは思うが、それ以上に生成AIを積極的に事業に取り込むなどしているのが米国を中心としたいわゆる「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大テクノロジー企業だ。
これまでに、マイクロソフト(Microsoft)、グーグル(Google)、アマゾン(Amazon) などが、オープンAI(OpenAI) や アンソロピック(Anthropic)といったベンチャーAI企業へ積極的に出資を行っており、自社サービスなどへの展開を図ってきている。
.jpg?width=704&height=383&name=202508-02_ph1%20(1).jpg)
オープンAIへの出資で抜け出した感のあったマイクロソフト
生成AIといえば「ChatGPT」といわれるほどに、一躍知名度が上がったのがオープンAIである。そのオープンAIに、マイクロソフトは 2019年7月に10億ドルを投資すると発表した。それまで非営利法人として活動してきたオープンAIが、 2019年3月に営利法人を立ち上げ、そこにマイクロソフトが出資をしたという経緯だ。
しかし、 2023年11月にオープンAIの創業者である サム・アルトマンが解任されるという事件があり、一時は騒然となったが、結果的にアルトマンは再び役員として戻ることになった。
オープンAIは営利法人としての顔よりも、非営利法人としての活動を基盤としたいという思いが 引き続きあるようだ。営利法人のオープンAIに出資しているマイクロソフトは、出資者と投資先のベクトルのずれを感じ始めているだろう。
マイクロソフトがオープンAIとの蜜月は終わったという判断をしている可能性は高い。例えば、2024年2月にはフランスのAIベンチャーであるミストラルAI(Mistral AI)と提携するに至っている。
オープンAIも、現在マイクロソフトと結んでいる契約を前提にすると組織の改変をしにくいということから、今後の資金調達を外部に求め始めた。2025年1月に、スターゲートプロジェクトを発表し、そのプロジェクトの出資者としては、ソフトバンクグループやオラクル(Oracle)などが株主として名を連ねている。
このように、マイクロソフトとしてはオープンAIへの出資を先んじて行っていたにもかかわらず、その後のマネジメントが思うようにいかなかったということもあり、現在はオープンAI以外の企業との提携および、自社での取り組みを中心とした体制に舵を切らなくてはならない状況に直面している。
オープンAIに投資していないプラットフォーマーの動き
AI領域において、自社モデルを活用し、先行していた印象があったのがグーグルだ。しかし、生成AIに関しては、マイクロソフトとオープンAIのコンビに先を越された印象は否めない。現在のグーグルは、独自の AIモデルであるGemini(ジェミニ)とアンソロピック社への出資を軸にAI戦略を進めているように映る。
アンソロピック社は、2021年にオープンAIの元社員ダリオ・アデモイとダニエラ・アデモイらが創業した AIモデル開発会社で、Claude(クロード)を開発している。Claudeは、特に日本のユーザーの間では、言語表現の流暢さなどに定評がある。2023年5月には グーグルおよび、セールスフォース(Salesforce)やズーム(Zoom)のCVCなどから出資を受けたという報道もあり、その後アマゾンなども同社に出資している。
グーグルやアマゾンといったマイクロソフト以外の大手テック企業が、オープンAIへの出資に出遅れた対応として、アンソロピックに投資をしているという構造だ。
【オープンAI陣営の動き】
| マイクロソフト | オープンAI |
|
|
出所:各種資料を元にモニクル総研作成
【非オープンAI陣営の動き】
| グーグル | アンソロピック |
|
|
| アマゾン | |
|
出所:各種資料を元にモニクル総研作成
巨大テクノロジー企業がAIにのめりこむ背景
ではなぜマイクロソフトやグーグル、アマゾン、セールスフォース、オラクルといったような巨大なテクノロジー企業が生成AIを得意とするAIモデル開発会社への出資を積極的に行うのか。その背景について、彼らのビジネスモデルや今後の戦略を含めて考えてみたい。
彼らの事業の特徴は、ビジネス向けのアプリケーションや関連するサービスを展開していることだ。特にアマゾン、マイクロソフト、グーグルなどは クラウドサービスの大手企業であり、 そうしたサービスの中でAIをどのように活用するかが今後の事業の差別化および競争優位の確立において重要となっているといえよう。
マイクロソフトはこれまで、企業向けの「Microsoft 365」をはじめとしたビジネスアプリケーションを中心に売上と利益の大半を構成してきた。現在は、そこに加えてクラウドサービスである「Microsoft Azure」が伸びており、同社のサービス別売上高の中で、最も大きくなっている。
マイクロソフトは、もともと企業向けビジネスアプリケーションでのシェアが高いことを強みに、今後ビジネスアプリケーションに「Copilot(コパイロット)」のようなAI機能を随時追加することで、さらに付加価値をつけるという事業戦略がしっかりはまってくると考えているだろう。
一方、グーグルは、広告事業が売上及び営業利益の大半を占めているが、現在は「GCP(グーグル クラウドプラットフォーム)」を活用したクラウドサービスやビジネスアプリケーションの展開に積極的になっている。
グーグルの広告事業においては、サーチ(検索)を通じて収益を得るリスティング広告や「YouTube」からの動画広告なども、これまで売上と利益を牽引してきた。このように、主体となる事業の規模が現在のように拡大すると、景気に循環する要因も出てくるため、将来にかけて事業を安定的に拡大できるビジネス向けクラウドサービスの展開が必至となっていると考えているだろう。
また、アマゾンも「AWS」というクラウドサービスを持っている。サービスの競争優位性を確立するためにも、競合企業の事業展開に対応するためにもAIの活用が重要となってきているだろう。
このように、生成AIは、ビジネス向けのクラウドサービスを提供する企業にとっては、現在最も注力して開発や実装に取り組むべきテーマとなっている。
マイクロソフトとグーグルの今後のAI活用の未来予想図
では、ここからはマイクロソフトとグーグルを比較してみよう。それぞれどのような課題があるのだろうか。
マイクロソフトは、2030年まで独占的にオープンAIの技術を活用できる。よって、現時点ではChatGPTの利用者増加の勢いを反映して、事業展開では優位性があるといえそうだが、 これまでのような蜜月関係を維持できなくなったということは先にも述べた。
したがって、その先の展開も考えるとマイクロソフトとしては、自社でAI開発に取り組むか、また提携先を拡大していくかの選択が必要な状況になっている。短期的には技術に関するリスクはないものの、中長期で見た時のリスクは意識すべきであろう。
グーグルは、自然言語処理などの研究開発を行ってきており、生成AI領域において、大きく先行しているようにみえた。しかし、ChatGPTの登場により、出遅れた印象となった。
マイクロソフトとオープンAIの今後の関係性についての不透明感が高まってきた中、グーグルは Geminiなどの自社開発の優位性を発揮できる可能性が、これまで以上に高くなってきているといえるだろう。
また、2023年以降行っているアンソロピックへの出資により、グーグルの自社技術だけではなく、アンソロピックを通じて自社に技術をフィードバックする、あるいは、自社サービスに付加価値をつけることができる可能性をも確保した。
一方で、クラウドサービスやビジネスアプリケーションにおいては、マイクロソフトに劣後していると言わざるを得ない。AIでどこまでビジネスアプリケーションの差別化ができるかが今後の事業拡大のポイントになってくるだろう。
AIモデル開発会社への注目度も高まっている今、大手テクノロジー企業のビジネスモデルの拡張や転換点をも考慮すると、生成AIの今後の動向から目が離せない。